
|
|
音円盤アーカイブス(2月) ジョー・ヘンダ-ソンが目的で、1992年の今頃岡山のLPコーナーで買ったCD。 ジョーへンがBLUENOTEからVERVEへ移籍して第一作目のビリー・ストレイホーン集をリリースするちょっと前に出たもの。 ウォルター・ノリスはジャズ喫茶でアラダー・ペゲとの共演盤を聴いたことがあるくらいで、あまり馴染みではなかった。 ジャケの写真を見ると、エディー・ヒギンズと同じ様な典型的なアメリカの人の良さそうな中高年白人男性の顔つきをしている。 ピアノ演奏は顔つきと同じ様に明快で歯切れが良く、品の良さを感じさせ乗りの良い調子でうたうタイプと思う。 やはり、個人的にはジョー・ヘンダ-ソンのテナーについつい耳がいってしまう。4曲目「NAIMA」ではウォルター・ノリスのソロによるテーマ提示から全員がフィルインしてややテンポアップして軽快な調子でプレイされる。5曲目「THIS IS NEW」や2曲目「WHAT‘S NEW」などバラードナンバーでもウォルター・ノリスのオリジナル曲やパーカー、コルトレーンナンバーでもジョー・ヘンダ-ソン流の独自の解釈、個性がどこかに感じられてやはりこの人テナー界のスタイリストなのだなぁとあらためて思う次第。 昔、こんな話を聴いたことがある。 ライブハウスでヘンダ-ソンの演奏を聴くと生音が凄く小さいのに説得力がとてもあって音の情報量が多いのにびっくりしたと・・・ ステージの後方に回るとほとんどテナーの音が聴こえなかったほど・・・ 音の小さい大きいは別の話として一音に込められるメッセージの情報量といったものは、凡百のテナー奏者が束になっても敵わないほど豊穣なクオリィティーを持ち合わせていた人だと思う。 2000年の春に広島の「ジャズニーズ」でケイコ・リーとデュオでツアーしていた吉田次郎にジョーヘンの容態をオフステージの時に聞いた。「調子が相当悪いらしくもうあまり長くはないかもしれない・・・」 それからあまり間をおかない内に亡くなってしまった。 録音は1991年8月13,14日 SAN FRANCISCO メンバーはWALTER NORRIS(P)JOE HENDERSON(TS)LARRY GRENADIER(B)MIKE HYMAN(DS) -------  パット・マルティーノのレコードを初めて買ったのは大学生の時で この「THE VISIT!」は2枚目に買ったもののはず。 三ノ宮センタービルに当時はAOIレコードがあってそこのエサ箱の中に偶然紛れ込んでいたのが当アルバム。 そもそもマルティーノは摂津「オアシス」の土曜会でギター研究家の樽さんがその才能の素晴らしさについて折に触れて言及されていたので、大学近くの行きつけのジャズ喫茶「JOKE」でもよくリクエストしてかけてもらっていた。 このアルバムや今はOJCで簡単に入手できるPRESTIGE盤などもよく聴いた記憶がある。 この「THE VISIT!」はCOBBLESTONEが消滅して版権がMUSEに移籍したのでその頃から既に足跡ジャケの「FOTTPRINTS」になってでていた。 街角の何の変哲もないセピア色したマルティーノのスナップ写真のジャケットに何故か当時から惹かれてMUSE盤の「THE EXIT」を買った後、当アルバムは是非オリジナルジャケで買おうとMUSE盤で手に入れるのを躊躇っていたのだ。 そんな矢先の出会いだったのでよく覚えている。 ほんの少しカットアウトされていたが、値段もそこそこ\2000ちょいだったので嬉々として買いあげた。 「JOKE」で何度も聴いていたので確認作業だけでそれはコレクションの一枚としてレコード棚に仕舞われた。 それから何年もたってこのレコードを聴きながらジャケットを眺めていて少し驚いた。 今まで何度か眺めているはずなのに全然気付かなかった。 マルティーノの着ているGジャンが私が勤めていた会社のものだと・・・70年初頭のものならば、状態にもよるがそこそこは現在するはず。もっともファーストや希少物はもっと価値が高いが。 このマルティーノ以外ではMAINSTREAM盤でチャールス・マクファーソンが着用してる。まだまだ探せばあるかもしれないが今のところお目にかかってない。 アメリカのB級映画やTVでは良くみるのですが・・・ 話が蛇足でした。 このアルバムについては有名な盤だし、とやかく言う必要もないと思う。ジャズファンならば一回は聴いておく必要のあるギター名盤じゃないかな。 選曲も非常に良くて愛聴盤になっている。 録音は1972年3月24日 PAT MARTINO(G)BOBBY ROSE(SECOND-G) RICHARD DAVIS(B)BILLY HIGGINS(DS) --------  EDUARDO CASALLAはアルゼンチンのドラマー。 EDUARDO CASALLAはアルゼンチンのドラマー。2年前仙台のDISKNOTEから通販でHPの推薦文につられるがまま買ったのだが、今になってアルゼンチンジャズに関心が個人的に高まっているし、買っといて良かったと思っている。 ピアノがERNESTO JODOSだし。 エルンストの湖面に拡がる円状の輪のような穏やかなピアノのイントロに続きJUN CURZ URQUIZAがストレートにストレイホーンの「ISFAHAM」を吹奏。ソロはピアノ、トランペットの順で1曲目から純正4ビートの高水準の演奏。 2曲目はERNESTO JODOSの作品。60年代の「ブラックナイル」や「ジュジュ」の頃のウェイン・ショーターが書きそうな曲。 軽快なテンポでありながら、メロディアスなソロのERNESTOがいい。リーダー、ドラムのEDUARDO CASALLAは決して主張するタイプのドラマーではないが、全員で音楽を作り上げていく、その為の土台をしっかりとささえるしっかりした技量と音楽性を持ち合わせたミュージシャン。 3曲目ショーター「YES OR NO」はややアップテンポ。 張り切ったトランペットソロが聴かれる。続くERNESTOの粒立ちの美しいピアノも快調。 ベースソロではじまる4曲目「JAULA DE LA LUZ」はピアノトリオで演奏される、穏やかな叙情性が感じ取れる曲。 5曲目はエバンス「RE:PERSON I KNEW」。 全曲と同じテイストの語り口。ここでもERNESTOのピアノの響きが美しい。アルゼンチンの石井彰だ。 6曲目はトランペッタ-URQUIZAの曲。ウディー・ショウが演りそうなカッコいい曲。 「I CAN`T STARTED」「MILESTONES」と続いてアルバムは終る。 アルゼンチンがストレートアヘッドなジャズにおいても結構よい演奏をするミュ-ジシャンがいるのが分かるアルバム。 2001年作品 --------  ようやくこの作品を紹介できる。 WOLF原盤の個人的名盤。 昔、1988年から1992年くらいまで大阪はミナミの名店「LIGHTHOUSE」の通販で毎月レコードを買っていたが、毎月送られてくるDISC REPORTが凄かった。今でも続いていると思う。 30ページの分量にジャケ写入りで細かく内容がレポートされていたのだ。裏表紙裏に塾頭Yab(藪元さん)という方が味のある文章でジャズに関するエッセイを書かれていて、その中でこのケニ-・バロンの「INNOCENCE」の事について触れられていた。 そんなにいいのだったら、是非聴いてみたいとその時から思っていた。 1994年に広島のファッションビル「ウィズワンダーランド」の催事広場でディスクマーケットが催された時、富山の中古屋さんが出展していてそこでこのレコードを発見した。 新宿の「木馬」が閉店した時放出したもの。何故分かるかといったらジャケット裏に小さく木馬のスタンプが押してあるから・・・ ケニ-・バロンはエレピを主に弾いている。 録音が1978年という事もあり、今の耳で聴くと時代を感じさせるサウンドの部分も無きにしもあらずだが、そのちょっと臭いところが逆に人間味を感じさせてとても魅力的。 ソリストとしてソニー・フォーチュンが3曲、ジミー・オーウェンスが2曲分け合っているが、断然フォーチュンのナンバーの方をよく聴く。 1曲目は必殺の哀愁メロディーをあのファットなトーンでソニーが奏でるとメロウ度は倍化される。 一度聴いたら耳から離れないシンプルだけど本当にいい曲だと思う。2曲目「INNOCENCE」も幾分ダークな雰囲気なマイナーチューン。うって変わって3曲目「BACCHANAL」は明るいラテンナンバー。 ケニ-のエレピも躍動しまくり、リズム陣も大活躍。 KENNY BARRON(KEY)SONNY FORTUNE(AS)BUSTER WILLIAMS(B) BEN RILEY(DS)RAFAEL CRUZ(PER)の布陣。 ケニ-・バロンが70年代後半残した最もフュージョン色の強いアルバムだとは、思うがやっぱりジャズなんですねぇ。 この人は・・・ 愛すべきB級作品。個人的名盤! --------  昨年の2月にサニーサイドさんから通販で買ったCDで、昨年のベストCDにも選んだもの。 ハーシュのアルバムではコンコード盤のピアノトリオが好きでよく聴いていたし、ビル・フリゼルとのデュオも持っていたが、最近遠ざかっていたので久しぶりに聴いてみようと注文したのだ。 トニー・マラビーが参加していたのもある。 1曲目「A RIDDLE SONG」からハーシュの非凡な作曲能力が窺える。ラルフ・アレッシとトニー・マラビーのフロント陣とピアノトリオとのダイナミクスの対比が素晴らしい。 「AND I LOVE HER」はうって変わって厳かな雰囲気で演奏される。ハーシュの宝石を散りばめたような美しいピアノの響きが曲調に見事にマッチしている。 4曲目はオーネット・コールマンや一頃のキース・ジャレットが書きそうな特徴のあるメロディーを持つ曲。 5曲目「A LARK」は題名通リ清らかでチャーミングなイメージの曲。ハーシュのピアノはなんとなく晩年のビル・エバンスを想起させる。アレッシがイマジネイティブなアドリブソロをとって好演。 7曲目「RAIN WALTZ」も雨に濡れそぼる大都会の風景が目に浮かんできそうな美しい曲。後半のトニー・マラビーのテナーサックスは大都会の喧騒を表現しているかのよう。クインテットのメンバー全員が一体化した写実的演奏。 9曲目の「LEE`S DREAM」もトニー・マラビーとハーシュの対話が興味深い演奏。 ラスト「THE CHASE」はテナー、トランペット、ピアノが追いかけっこする曲。 ハーシュはエイズを発症して以来も精力的に演奏活動を継続させていて今のところ元気なようだ。 作曲と演奏、グループサウンドとしてのアレンジメントの能力にもますます近年その才能を発揮しているので今後にも期待したいアーティストだ。 録音は2003年9月23日 MAGGIE`S FARM NY FRED KERSCH(P)DREW GRESS(B)NASHEET WAITS(DS) RALPH ALESSI(TP)TONY MALABY(TS) ---------  去年の夏、タワーレコードで試聴して以来その噂に違わぬ素晴らしさにいつか買わねばと思っていた名作。 一昨日ようやく広島のタワーレコード(タワー限定盤らしい)で買った。 アルゼンチンのギタリストが作り上げた最高のボサノバ作品のうちの一作だと思う。飛行機の前の人物像のジャケなら、ジャズファンならば、チェット・ベイカーやピム・ヤコブを思い浮かべると思うがこの作品のジャケも実にイイ。 ボーカルのマリア・ナザレスは乾いたトーンの声の持ち主でそのドライな声がブラジル音楽の名作に見事にマッチしており、本物のサウダージが感じ取れる。 ジャケット左のアルナルド・エンリケスも味のあるボーカルを披露。 本場ブラジルではとっくにボサノバの時代ではなかった時、(1973年)隣国アルゼンチンで生まれた三位一体、奇跡的なボサノバ作品。 ブラジル音楽を愛する全ての人に一度は耳にして貰いたい一作。 これを聴いたら、 遠い日の眩しい太陽の光と乾いた風の想い出が甦ってくる・・・ ---------  1987年4月の発売と同時に買ったCD。 当時日本人で初めてコロンビアと契約した驚異の新人ピアニスト登場という形で小曽根真は大々的に売り出された。 それにも拘らず、根がひねくれているのか何故かデビュー作、2作目とパスしてようやくこのアルバムになって手に入れた次第。 何ヶ月か前にゲイリー・バートンのECM盤「神童」で小曽根がピアニストで参加はしていたが、リーダー作で本格的に聴くのはこの時が初めてだった。 数年後、AM神戸(ラジオ関西)で土曜の昼、父親の小曽根実がディスクジョッキーを務める番組があって、営業車に乗りながらよく聴いていた。その中で息子の真に電話するコーナーがあって、実「マ-ボーちゃ--ん」真「なんやぁー。親父ぃー」みたいなモロ関西のノリの二人の漫才みたいな軽妙なやり取りが面白かったのを覚えている。今なにしてるのかとか、今週のスケジュール予定とかレコーディングの話とか最近はまっている事とかたまには裏話が聞けたり10分ほどの電話話だったが車を止めて聴いた事もあるくらい楽しみなコーナーだった。(1992、3年位から大震災の前までだったと思う)その後小曽根真の方がKISS FMでレギュラー番組を持つようになったのは記憶に新しい。 こんな事を最初に書いたのは、 このピアノトリオ作を聴いていると何故かその番組での小曽根の面白おかしくも理路整然とした頭の良さを感じさせる喋りを思い出したからなのである。 デビュー当時ピーターソンやチック・コリアの影響が大きくて独自の個性に欠けるきらいがあるとの批判が一部のクリティックにあったがこのアルバムを聴くとそんな批判をものともしない天真爛漫にピアノを弾くのが楽しくて楽しくて仕方がないといった小曽根の姿が捕らえられていて、さっきの「喋り」のようなピアノプレイが実は小曽根の個性だったということがわかったのである。 この人、感覚派や圧倒的なアドリブを繰りひろげる天才プレイヤーでは決してない。しかし、全てのプレイが全部自分でわかってやっている音で演奏しているように思えてならない。小曽根式脳内コンピュータープログラミングによってその場その場でいかにすれば最高の演奏になるかといったことが理路整然とコントロールされて瞬時に肉体に連動してパーフォーマンスに具現化されるのだ。 もちろん最高の演奏というからにはジャズの持つ即興性、人間身のある暖かさなどもインプットされているのは当然だ。 悪口を言っているのでは決してない。 小曽根は日本人ピアニストだ3本指に入ると個人的に思っているし 現行のTHE TRIOもこれ以上どこにいくのだろうというくらい高みに登りつめたと思う。 だから、一度慌てふためいて半分パニックになったような必死に冷や汗たらしながらピアノ弾いている小曽根の姿を見てみたいと思うのは残酷すぎるだろうか? 何か人があっと驚くようなプロジェクトでそんな姿を一度見せてくれません? 小曽根さん・・・ 録音は1986年12月 NY 小曽根真(P)GEORGE MRAZ(B)ROY HAYNES(DS) -------- 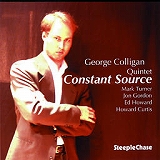 STEEPLECHASEから出たデビュー作はすぐに買っていて何でも器用にこなす白人の新人ピアニストだなぁという印象を持っていた。 当アルバムはSTEEPLECHASE4作目にあたり、マーク・ターナーとジョン・ゴードンがサックスで参加していたのでどんな感じなのか興味が湧いて買ってみたのだ。 1999年の夏、仕事の市場調査で大阪に土曜日、日帰り出張した際、帰り際ワルツ堂EST1店で買った。 日中は前夜、イタリアンレストランでワインを飲みすぎて二日酔いでアメリカ村の辺を歩いている時倒れそうなくらい暑くてきつかったのを覚えている。 買ったときは夕方だったし二日酔いもおさまっていたので一時間くらいで10枚くらい選んで買って帰った。 1曲目、アップテンポのモードナンバーは、ツーサックスのテーマ提示の後、迫力ある押し進むようなピアノトリオによる演奏になり、マーク・ターナー、ジョー・ゴードンとソロが継がれる。 サックス勢の二人は抽象度の高いクールなプレイでジョー・ゴードンは自身のアルバムとは大分印象が違ってこんなプレイもこなすプレイヤーなのが分かった。 ドラムのハワード・カーティスは張り切ったプレイなのだが、スネアがドタバタしてやや小うるさく聴こえて損していると思う。 コリガン自身のソロは、昨日の小曽根真のところでも書いたが、ケチをつけるところがほとんどない完璧なテクニックを身につけた素晴らしいものなのだが、完璧なのが逆に損しているというか、面白みにかけるところ無きにしも非ず。 もう少し不良性がでてきたらもっと器の大きなミュージシャンになれる可能性を秘めていると思う。 実際、最近はハモンドB-3なども弾いて一皮剥けたプレイを披露しているようなので最新作も早くチェックせねばと思っている。 4曲目「I`M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU」以外は全てコリガンのオリジナル作品でまとめられている。 5曲目「PITCHRIDER」ではコリガンはエレピを使用。カッコいいソロを展開。ライナーにゲイリー・トーマスに作曲面で影響を受けたとあるが、そう聞くと、この曲でのターナーのソロなどトーマスのソロに聴こえなくもない。 7曲目「MY EYES THAT CRIED」は秀逸でメランコリックなスローナンバー。フェンダーローズの音が美しい。 ラストは表題曲「CONSTANT SOURCE」。日頃、作曲面でとてもインスパイアされているゲイリー・トーマス、マーク・ターナー、ゲイリー・バーツ、カート・ローゼンウィンクル、デビッド・ギルモア、グレゴリー・ターディーに捧げるとライナーにある。 録音は1998年4月 -------- 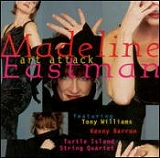 そのブルーグレイの引き擦り込まれるように奥深い目の色と同じ様なボイスがこの歌手の大きな武器だ。 ジャケットにトニー・ウィリアムスとケニー・バロンの名前を発見した事も購買動機を促したと言える。 倉敷のGREEN HOUSEで入手した。 セッションはケニー~トニーのピアノトリオ中心のものとパーカッション、ギターが入った無名のミュージシャンのセッションに大別される。 聴いてみてこれが、無名連中とのセッションの曲のほうが、良いのですねぇ。トニーのトリオがまずい伴奏というわけではなく相性というか、曲とメデリーンの唄と演奏とのマッチングが前者の方が私にとっては好みだったと言うべきか? 1曲目「THE THRILL IS GONE」アコースティックギターのゆるやかなボッサリズムにのって滑り込むように入ってくるメデリーンの深く情緒豊かなボーカルに一辺に心を奪われてしまった。 素晴らしい出来映えだと思う。 3曲目「SONHOS」は明るい曲調で、晴れわたった日に湾岸道路を車でドライブしているような爽快な雰囲気のブラジリアンテイストな曲。 ラストのボブ・ドロー作「LOVE CAME ON STEALTHY FINGERS」はアカペラで唄われ曲の最後の方で1曲目の冒頭に使われたサウンドエフェクトが同様にインポーズされる。 トニー、ケニーのピアノトリオの伴奏曲は7曲でこれはこれで決して悪い出来ではない。 録音は1994年 キティー・マーゴリスと共同で営むMAD-KATレーベルからのリリース ---------  1988年だったか、岡山のLPコーナーから送られてくる通販リストを見て、これは買わねばと条件反射のように反応したのがこのレコード。ギル・エヴァンスとスティーブ・レイシーの共演! 「ギル・エバンス・テン」や「個性と発展」以来の事ではないか? しかも完全なデュオって初めてでは? 期待に胸が高まった。 1曲目チャールス・ミンガスの「REINCARNATION OF A LOVEBIRD」 ギルのエレピは高名な書道家の一筆書きのように、自由に駆け巡る。浮遊感を残しながらブルース感覚を明確に伝えてくるワンアンドオンリー、ある意味天才的なキーボードプレイを披露してくれる。実際ギル・エバンスのキーボードプレイがこんなにたっぷりと聴けるアルバムは今までなかったと思う。 一方のスティーブ・レイシーはいつもの様に唯我独尊、あの思慮深いと言ったらよいだろうか、一音でレイシーと分かる誰も到達した事のない言霊が宿っているとしか言いようのない深い音色でフレーズを紡ぎだす。 ギルもレイシーもいつもと違うことをやっている訳ではないのに何故か、この二人のプレイ不思議なくらい調和して、素晴らしい共演盤と相成った。 レイシーと言えば、ジャズを聴きだした当初、「JAZZ MAGAZINE」か「JAZZLAND」のどっちかだったと思うが、間章のレイシーへのインタビューが掲載されたことがあった。 その中でセシル・テイラーとのフリーフォームの演奏の特訓でテイラーのワンコードが鳴っている間にあらゆるノーツを吹き続けるという練習があったそうで、その体育会系の猛特訓に普通でない匂いを感じ取りその頃から私にとってレイシーは要注目のミュージシャンになった。 その頃読んだ植草甚一の「森と動物園」のことについて書いた一文を読んでますます興味をもった。 レイシーのレコードを今ではそこそこ所有しているが、生演奏は残念ながら見ないで終ってしまった。 見ようと思えば見れたのに見ずに終って後悔しているミュージシャンはこのレイシーとアート・ペッパー、チェット・ベイカー、ミンガスであります。 このレコード、やはりB面の方をどちらかというと良く聴く。 ミンガスの中でも特に好きな2曲を続けて演ってくれているから。 ジョニ・ミッチェルの「PORK-PIE HAT」でのウェイン・ショーターの演奏も最高だけどこのスティーブ・レイシーのプレイはさらに超越した何かを感じる。ギルのエレピも銀河系宇宙の中で一番ヒップだと形容してもいいくらいカッコイイ。 奇跡的な美しさを感じ取る最高のジャズ、最高のデュオ演奏だと思う。 録音は1987年11月30日、12月1日 PARIS ---------  あのヨーロピアン・ジャズ・トリオのマーク・ヴァン・ローンである。このCDではこれが同一人物かと思うほど、ハードで硬質なプレイをみせている。 六本木WAVEから通販で購入した。買った理由はデイブ・リーブマンが全面的に参加していたから。 1曲目ジャズロック風のビートにデイブ・リーブマンとマーク・ヴァン・ローンがノリの良いソロを展開。もっともリーブマンはかなりフリーブローイングだが・・・ 2曲目はリーブマンのもうひとつの特徴が発揮される瞑想調と言えばよいのか、耽美的でメランコリックなレーベルでいえばECMっぽい曲調。ローンのソロも美しい。 3曲目はJASPER BLOOMというテナー奏者が参加(7曲目も)していて、リーブマンのSSとツーサックスの編成。4ビ-トのリズムの中をリーブマン作の複雑なテーマをもつ曲が演奏される。 4曲目はアルバムタイトル曲「FALLINGSTONE」。 これもスローな乳白色の厚くおおわれた北欧の雲を思わせる様な曲な思索的な雰囲気をもつ曲。 5曲目はC.VISENTINとリーブマンとの共作。ふたりの頭文字をとった「C+D」。4ビートの比較的聴きやすい曲。 ベースのTONY OVERWATER作の6曲目「SEE KAY」これもややアブストラクトな曲調のテーマをもつ曲だが、ソロに関しては逆に結構聴きやすいと思う。 7曲目はリーブマンの「ドリアン・グレイの肖像」。 ヨーロッパフリーの雰囲気の導入部からルパートで演奏され続ける。 9曲目はドラムのソロから始まる4ビートのこれもリーブマンらしいクロマチックな音列からなるテーマからアグレッシブなソプラノのソロへと続き熱演である。 ラストはローンのヨーロッパの古城のほとりを散策しているような気分になるメランコリックで少し妖気を漂わせたような曲。 全体的にアーティスティックでやや空回りしている部分無きにしも非ずのサウンドであるが、やりたいことを真剣に表現してみせた気概が感じられ、マーク・バン・ローンもこんな音楽指向の面もあるんだという事がよく分かるアルバム。 最近、中古で「哀愁のヨーロッパ」ヨーロピアンジャズトリオにジェシ・ヴァン・ルーラーが参加した日本盤を\409で入手した。 1曲目の「ヨーロッパ」なんか結構よく聴くのですが、このMONS盤とどちらかを選べと問われれば、何の迷いもなくMONS盤の方を私は選ぶだろう。 録音は1994年4月 オランダ ---------  福岡のキャットフィッシュレコードのHPを見ていてトロンボーンのワンホーン物だし、選曲が私の好きな曲ばかり入っていたのでED KROGERの名前は全く知らなかったが直ぐに注文した。 2000年の3月の事。 収録曲は「SPEAK LOW」「WHAT`S NEW」「WHISPER NOT」「ESTATE」「IT`S YOU OR NO ONE」「FOR ALL WE KNOW」「BLACK NILE」「OLD FOLKS」「ALONE TOGETHER」 うーん・・・やはり好みの曲だ。 特にESTATEとBLACK NILE, SPEAK LOWとWHISPER NOTも・・・ ジャケにROMY CAMERUNという女性ボーカルのクレジットがあった。どちらかというとトロンボーンの純正ワンホーンでアルバム一枚聴きたかったというのが本当の気持ち。 1曲目「SPEAK LOW」からボーカル入り。決して悪い歌唱ではないのだが、如何せん私の好みではないのだなぁ。 ボーカルに関しては、徹底的に昔から個人の好みで、つまり好き、嫌いで判断している。このボーカリストはやや鼻にかかった少し粘りのある声質なので、あまり好みではないのだ。 SPEAK LOWとWHISPER NOT,ESTATE、期待していた曲全てボーカル入りだった為いささか拍子抜けしてしまった。 もっともED KROGERやピアノのMATTHIAS BATZELの間奏は聴いていてとても曲調を理解した暖かくメッセージが伝わってくるプレイ。 ESTATEの歌唱もやや本人に荷が重かったのではなかろうか? 5曲目からインスト曲が多くなり、今ではアルバムの後半から聴くことが多い。 7曲目の「BLACK NILE」。ウェイン・ショーターの同曲はやはりシンプルすぎるくらいシンプルだけど、名曲だと思う。 この曲が収録されているとついそのアルバムが欲しくなってしまう1曲である。ED KROGERも熱演。トロンボーンに関しては中庸の上手さというか、テクニシャンではないが歌心の富んだプレイで説得力がある。OLD FOLKSも素晴らしいワンホーンバラードに仕上がった。 ラストは「ALONE TOGETHER」。通常よりやや早めのテンポで演奏される。 録音は1999年3月30,31日 ハノーバー ---------  テナー奏者でリズム面やその独特のフレージングに影響を受けているプレイヤーは大勢いると思うが、音色そのものからジョー・ヘン直系のプレイヤーはこのEcKHARD WEIGTが初めてじゃなかろうか? 2曲目「ROLLINISSIMO」短いフレーズやジョーヘン独特のウネウネとしたフレーズ、トリルなんか本当にそっくりに聴こえる。 ピアノはMARTIN SCHRACK,最近名前を聞いたような気がするが、思い出せない。ベースはTHOMAS STABENOW、この人は結構有名。 3曲目はチャーミングなスローナンバー。サブトーン気味にフレーズをデクレッシェンドして終らせていくフレーズなど本当によく似ている。 4曲目「SIENA」軽快な4ビートナンバー、快調にジョーヘンマナーでテナーを吹くWEIGT。ここまで聴いて考えた。 「似ているのは良しとして、この奏者の個性ってなんなんだろう?」と・・・ 今はよいとして、将来もこのままジョーヘンのそっくりさんのままじゃいずれ飽きられるだろう。 ジョーのスタイルはジョー・ヘンダーソン・オンリーのもの。 スタイルの真似自体誰もがコピーして自身のスタイルを形成していく過程で経験すること。決して無駄なことでもないし、悪い事でもない、むしろ勉強の意味では有意義なことだと思う。 ローカルなジャズシーンで活躍するにはそれで充分なのかも知れない。しかし、ジャズ村の中央へ出てきて誰からも認められるプレイヤーになる為にはそこから絶対といっていいほど抜け出さなくてはならないところだと思う。 作曲もいいセンスしていると思うし、ジョーヘンスタイルを消化し、そこから脱却した新しいEcKHARD WEIGTのプレイを今度は聴いてみたい。 録音は2000年2月26,27日 ---------  六本木WAVEの広告で興味をもって1994年1月に通販で購入したCD。 買ったとき、リーダーであるトランペット奏者ROUSSELETの名前は知らなかったが広告の掲載文を信用して買ったのだ。 ギターのJEANFRANCOIS PRINSやピアノのMICHEL HERRの名前は知っていたし曲も「DEAR OLD STOCKHOLM」はじめとして有名曲が多く収録されているので大きくはずすことも無いだろうと考えたのだ。 その1曲目「DEAR OLD」なのだが、テーマは編曲しすぎ、もっとストレートに吹いたほうが曲の良さがそのまま出てよかったのではないか?アドリブの方はミュートトランペットで結構渋いプレイ、実力が窺える。2曲目はROUSSELETのオリジナル。曲名通りバップイディオムに基づいた作品でスムースに展開する流れ。ジャンフランソワ・プリンもルネ・トーマを思い出ださせる太いギタートーンで歌心溢れたプレイを披露。 3曲目はブルージーな曲調でミュートトランペットでテーマは吹奏される。ミッシェル・ハーの叙情感のあるピアノソロが中々よい。 不穏な雰囲気から4曲目「CARAVAN」は始まる。サビ部分で少しビブラートをかけたオープンホーンにミュートから切り替えたアイデアが曲に変化をもたらせて面白い。編曲はベースのJEAN-LOUIS RASSINFOSSE。 5曲目フランク・フォスターの名曲「SIMONE」。 ROUSSELETのトランペットが映える曲でベストの相性をみせる。 このアルバムの一等賞じゃないかなぁ? ミッシェル・ハーも流麗なソロを展開、実力をみせつける。 7曲目アルバム表題曲「WAITIN` FOR YOU」はジャケットの写真のような夜明けのイメージを想起させるやや絵画的なJ・PRINSの曲。 8曲目はトランペットとギターがユニゾンでテーマを奏でる楽しげな雰囲気を醸し出すテーマが良い。 ラストの「WHAT」まで快適な演奏が続く。 曲によってはモンクの曲など凝ったアレンジで変化もつけていて飽きさせない。ベルギージャズの中堅どころの水準の高さをみせつけた一枚と言ってよいと思う。 録音は1993年4月 BRUSSEL -------- 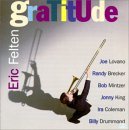 このCDもリーダーのERIC FELTENが一番無名であとのメンバーは全員名の知れたミュージシャン。 JOE LAVANO(TS)RANDY BRECKER(TP,FLH)BOB MINTZER(B-CL)JONNY KING(P)IRA COLEMAN(B)BILLY DRUMMOND(DS)といった具合である。 このアルバムは彼の2枚目のリーダー作でデビュー作も同様にSOULNOTEからリリースされている。 アリゾナ州フェニックスの生まれで、祖父が東海岸のスイングバンドのトロンボ-ン奏者だったこともあり、9歳の時から始めた。 このアルバムでは、1930年代のエリントンのスモールコンボのサウンドを現代的な解釈をまじえ再現することを狙いとしたそうで、1曲目のホッジスの「JEEP`S BLUES」から古き良き時代の作品が流れてくるといった仕掛け。但し、各プレイヤーのアドリブは 当然といってよい位、現代的でオリジナルなサウンド。 ランディー・ブレッカー、ジョー・ロバーノのソロが聴きごたえがある。ピアノのJONNY KINGもこの頃から頭角をあらわしてきた新人で、CRISSCROSS,ENJAから立て続けにリーダーアルバムをリリースしていったが、最近あまり名前を聞かない。どうしているのだろう? 2曲目からはERIC FELTENのオリジナル作品が続く。 ソロオーダーはフェルテン、ロバーノ、ミンツァー、キングの順で極めてオーソドックスな楽曲にモダンで個性的なアドリブが快調につながれるといった按配。 3曲目はスローナンバー「GRATITUDE」こういう曲でのロバーノは最高に光ってみえる。続くFELTON君も個性という点ではロバーノにひけをとるが、健闘してプレイを披露。トロンボーンの楽器特性を活かした暖かく説得力のあるプレイなのがいい。 5曲目は急速調のテーマに続きランディー・ブレッカーのキレの鋭くスリリングなソロが爆発、続いて例のとぐろを巻くようなスタイルのソロにつながれる。キングも新主流派から現代ピアニストのスタイルを消化した熱気に溢れたソロを展開、最後にFELTENが締めくくる。 7曲目は「I FALL LOVE TO EASILY」甘くノスタルジックな響きを含ませつつモダンな解釈でバラードをプレイするフェルテンの実力が窺えるトラック。 8曲目「THE KING IN YELLOW」はレイモンド・チャンドラーの短編小説を読んでそのフィルムノワール的な雰囲気の曲を書こうと思いたって作った作品。 9曲目はボブ・ミンツァーのバスクラが活躍。 ラストはアルバム表題曲「GRATITUDE」がFELTENのジェントルな奏法で優しく奏でられる。 今月、VSOPから新作をリリースしたFELTEN、その音楽指向はこの頃よりオーソドックスでエンターテイメントなサウンド指向になっているようだ。 録音は1994年3月17日 NY --------  チャールズ・ロイド、シダ-・ウォルトン、バスター・ウィリアムス、ビリー・ヒギンズからなるレコーディングセッションのグループ名。チャールズ・ロイドはECMから一年に一枚ペースでリーダーアルバムをリリースしているが、このアメリカンリズムセクションとの共演はどんな感じで演っているのかと思い購入したのだと思う。 ビリー・ヒギンズの特徴あるスネアのリズムに導かれてチャールズ・ロイドのテナーが自由奔放に響き渡る1曲目のブルースチューンからグイグイと引き込まれる。抑えようとしても純度の高いジャズの香りが止め処なくほとばしり出る感じと言ったらよいだろうか? 2曲目はシダ-・ウォルトンの「CLANDESTINE」。チャールズ・ロイドはECMの自身のリーダー盤よりリラックスした自由奔放なソロを取っていて、書道の大家の一筆書きのように擦れたり、太くなったり細くなったりした字がある位置から見たらものの見事に素晴らしい芸術作品になっているのと同じ様にユニークで説得力のあるワン&オンリーなアドリブを展開している。 3曲目も1曲目と同じ様なテイストで曲が進む。 ノリのよいロイドのテナーとスインギ-なウォルトンのピアノソロが味わえるトラック。 4曲目はこのアルバムのベストトラックであろう「LADY DAY」。 人生のいい時もどん底の時も経験してきた1993年の時点のロイドでしか表現できなかったであろう深くそしてとてつもなく優しいバラード。6曲目「STRIVERS JEWELS」もジャズ喫茶のほの暗い空間で聴いたら最高だと思うスローナンバー。 全部で8曲が収録されている。 レ二-・ホワイトがプロデュースした90年代前半のアコースティックな隠れ名盤の一枚だと思う。 録音は1993年7月 --------  ジャケ写がなんとなくスティーブ・グロスマンに似ていないか? PIERO ODORICIが2002年のTRENZANO JAZZ FESTIVALに出演した際のライブ録音盤。一昨年の冬にサニーサイドレコードから通販で買ったもので、お気に入りの曲「ESTATE」が収録されていたから、興味をひいた。1曲目にEDU ROBOの名曲「REZA」を演っているではないか! 個人的には中村善郎やカルテット・エン・シーで耳馴染みになっているこの曲をハードドライビングにブロウするPIERO ODORICI。 原曲の厳かで感傷的なイメージは吹き飛び躍動感溢れるモードジャズに変換された。原曲の存在が大きすぎて正直今一歩ピンとこない。もと歌を知らないほうが純粋にジャズ演奏として楽しめるのかもしれない。 2曲目はお目当ての「ESTATE」なのだが、サックス演奏でこの曲のいい演奏にあまりお目にかかったことがない。曲と楽器の相性ではピアノ、ギター、トランペットなんかの方がマッチしていて名演も多いと思う。 聴いてみてなかなかPIERO ODORICIの演奏が良いのである。 無心に吹いたのが良かったのであろう。この曲メロディーが命の曲と言って良いのではなかろうか?邪念が入らずにメロディーをほとんど崩さず少しぶっきらぼうと思えるくらいストレートに吹いたのが成功のもとだ。アドリブもメロディーの断片、フェイクを散りばめつつ常にテーマの変奏風にまとめたのが良かったのだ。 ライブ会場の聴衆の拍手がひときわ多く聴こえるような気がする。 4曲目「LIMEHOUSE BLUSE」はアップテンポでODORICのテナーはスティーブ・グロスマンを彷彿させる。ギターもピアノも熱気に溢れたソロを展開して好演。 ラストの「I THOUGHT ABOUT YOU」はミディアムで演奏。 この曲はやはりスローテンポの方がよい。ライブ演奏という事もあるが15分はちょっと冗長に聴こえる。 中堅といってよい1962年生まれのイタリアのテナー奏者PIERO ODORICIの近況を伝える一作。 テナーの技法は素晴らしい才能を持っているので後はいかにもっと自身のオリジナリティーを深めそれをアピールしていくかが、課題であろう。 録音は2002年7月11日TRENZANO JAZZ FESTIVAL -------- 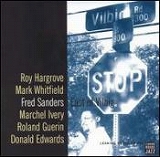 1999年にキャットフィッシュレコードの広告を見ていて欲しくなり通販して手に入れたもの。メンバーにROYHARGROVEとMARK WHITFIELDの名前を見つけたのが購買動機となった。 FRED SANDERSは最初セロを学んでいたが高校時代ROY HARGROVEの演奏を目の当りににしてセロでは共演する事が難しい為ピアノに本格的に転向したらしい。そのピアノスタイルは決して器用ではないが、伝統的な黒人ピアニストの系譜をひくダウン・トゥ・アースな面も持ち合わせる骨太なピアノ。細部のテクニックより雰囲気全体で音楽を表現するタイプと言えばよいだろうか? このファーストアルバムは全部自身のオリジナル作品で構成していてオーソドックスなハードバップ、ブルース、ウィントン以降のリズム構成にキレがある新主流派風の曲と結構バラエティーに富んでいて飽きさせない。 メンバーの中ではロイ・ハーグローブが自身のアルバムよりずっとリラックスしたソロを取っていて、リー・モーガンやルイ・スミスを曲によっては彷彿させるものがある。 マーク・ホイットフィールドもサトルで歌心溢れたプレイを展開。 そんな感じなので昔のBLUE NOTEやRIVERSIDEのレコードを聴いているような気分になる。テナーのMARCHEL IVERYはさしずめジョージ・コールマンとティナ・ブルックスを足して二で割った感じか? ともあれ現代の黒人ミュージシャンによる快適でリラクゼイションに富んだ黒人特有のレイジーでブルージーな面を昔のセッションの様に曲によってはプンプン臭わせたほのぼのとしたセッション盤となったと思う。 メンバーは ROYHARGROVE(TP,FLH)MARK WHITFIELD(G)MARCHEL IVERY(TS) FRED SANDERS(P) ROLAND GUERIN(B)DONALD EDWARDS(DS) 録音は1997年6月 --------  最初はドラムのマット・ウィルソンのメンバーのテナー奏者という事で名前を知った。 そのマット・ウィルソンのグループの写真で本人の姿を見たのだが、プロレスラーのような胸板の厚い巨漢で、この体躯でテナーをまるでアルトの様に楽々と吹きまくり鳴らしまくるのかと思ったら、結構優しく深みのある音色で丁寧に楽器を吹くスタイルなので、見た目と違う印象をもった。 このPALMETTOからリリースされたリーダーアルバムでも基本的にその印象は変わらない。 もっとも曲によってはブロウしてフラジオで高音域のフレージングやハーモニクスによる演奏上の工夫が見受けられるが、うるさく聴こえないというか、排気量の凄いスーパーカーが低速で軽く流している様な余裕がものすごく感じられるのだ。 4曲目「THE NAVIGATOR」はアップテンポの4ビートナンバー。 ビリー・ドラモンドとスコット・コリーのつむぎだす極上のリズムの上をその余裕のテナーが疾走する。 疾走しているのだけれど、スピードは感じない。 地に足がしっかりついたと言えばよいのか、周りを見回しながら全体のサウンドを構築しつつ自己表現していくタイプなのかもしれない。そういう意味でJOEL FRAHMは調和の人、協調の人なのだと思う。 体型と同じように胆の据わったどっしりした印象をどんな速いフレーズを吹いても受けるというか、プレイに安定感があるのだ。 そんなFRAHMだから、もしぶちぎれたプレイを何かの拍子にやらかしたら一体どんなプレイをするのだろう? そんなシチエーションでの切羽詰まった演奏も聴いてみたいと思うのは残酷なファン心理か? マイルド、スムージー、ドリーミーな「MY ONE AND ONLY LOVE」。歌心もとてもあるテナープレイヤーと見た。 もっと注目されても良いと思う。 8曲目「FORT WAYNE」は題名通り60年代のブルーノート時代のウェイン・ショーター風の曲で、FRAHMの演奏はオリジナリティーに溢れ説得力がある。 ラストはデビッド・バークマンの幻想的な色調を帯びたイントロから始まる「SISTER JULIE」。 最後はすこしECM風に締めくくられる。 録音は2000年5月26日 MAGGIE`S FARM --------  昨年末阪神百貨店の中古市で買ったCD。 最初はなんとなくジャケットに惹かれDAVID REXという名前にもなんか聞いたことがあるようなないような、といった感じで以前ディスクユニオンからこのアルバムの前作を買ったことをすっかり忘れていた。気がついたのは一通りチェックし終えたCDの品定めを売り場の片隅でしていた時に気がついた。当然、前作が良かったので直ぐに購入が決定した。 DAVID REXはオーストラリアの新進アルト奏者でそれ以外の詳しいことは知らない。 ケニー・ギャレットばりの直情的でエグミ成分を含んだところがあるかと思えば、ジョージ・ロバートのように丸みと滑らかさを伴った輝かしく艶やかなアルトの音色も出すといった具合でまだ完全に自身の音を完成したプレイヤーではないのかもしれない。 それでもこの人の音色はどんなフレーズでもダークな部分を含んでいてそこがジャズを演奏するのに大きな武器になっていると思う。 4曲目「BRIGID」。女性の名前の曲に良曲多しとは私の持論だが、この曲もそこはかとない淡い哀愁が感じられるイイ曲だと思う。 このアルバムではオリジナル5曲とジャズオリジナル、スタンダード5曲と仲良く分け合っている。 5曲目はビル・エバンス「VERY EARLY」。 やや平板な印象を受ける。サックスにはもともと相性が良くない曲かな? ストレイホーンの「CHELSEA BRIDGE」。 高音部でのホッジスのようなビブラートはなかなかのもの。 8曲目マッコイの「BLUES ON THE CORNER」。 テナーの印象が強い曲だが、REXはアルトサックスで健闘している。自分が持てる力を精一杯使って誠実に演奏しているところに好感がもてる。 もっともジャズ演奏の場合、当然それだけで素晴らしい演奏になるわけではないので、REXにはこれから色々な経験を積んでいくことによって、より個性的で深い演奏ができるミュージシャンになる事を期待する。 2001年オーストラリア作品 --------  このCD、LABELBLEUレーベルだが、INDIGOの方なので純然たるジャズではないと思っていた。実は一昨日、ぼたん雪の降りしきる倉敷のいつも行く中古屋「レコード屋」の新着(ワールドミュージック)のコーナーで発見したもの。\1290だった。 編成はバンドネオン、バイオリン、ピアノ、ベース、ギターのクインテットでタンゴは全くといっていい程聴いた事がなくてよく分からないのだが、これはジャズ的な耳で聴いても相当凄いCDなんじゃないかと思う。 まず、音楽にパワーが満ち溢れている。そして色彩感に富んでいて多彩な表情を曲が進むにつれ体感できる仕組みになっているのだ。 個々の楽器奏者のテクニックも完璧でおそらくキチンとアレンジされた譜面をもとに演奏されたものだと思うが、そこから下手なジャズより数倍生き生きとしたミュージシャンのメッセージが聴こえてくる。一般的なタンゴのイメージよりもっと汎世界的というか、地域に限定されないエスニック性を感じる音楽。 タンゴについてまわる音楽的イメージ例えば、哀愁、叙情それも確かにたくさん感じられるのだが、それを踏み越えた人間の情感の裏の部分、ドロドロとした暗黒性みたいな部分までこの音楽は表現しているように思えてならない。 「ブイレスアイレス午前零時」という言葉がしっくり合いそうな4曲目「DESDE ADENTRO」。 深夜1人で聴いていたら、まるで自分が地球の裏側で人生の孤独なエトランゼになった様な気分になること受け合い。 ラストは「NAOMI」日本の女性名から採ったものなのか? 謎である。ライナーにその曲の由来は触れられていない。 メンバーは、JUAN JOSE MOSALINI(BANDONEON) ANTONIO AGRI(VLN)OSVALDO CALO(P) LEONARDO SANCHEZ(G)ROBERTO TORMO(B) 録音は1996年4月 -------- ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|
||